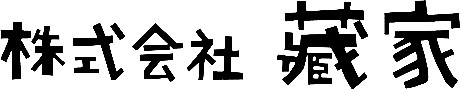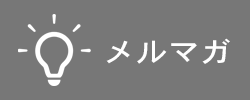【リフォーム屋と工務店の違い】失敗しないリフォームのために知っておきたい新常識【2025年最新版】

家のリフォームを考えるとき、
「工務店に頼むべきか?それともリフォーム屋さん?」と迷う人は少なくありません。
実はこの2つ、見た目は似ていても、家に対する考え方や対応できる範囲がまったく違うんです。
さらに2025年4月の法改正で、確認申請が必要な工事の範囲も大きく変わり、「今まで頼んでたリフォーム屋さんにそのままお願いして大丈夫?」というケースも増えてきました。

今回は、リフォームの前に知っておくべき「業者選びの分かれ道」について、事例も交えながらわかりやすく解説していきます。
目次
- 1 1. リフォーム屋さんとは?
- 2 2. 工務店とは?
- 3 3. 成り立ちの違いが何に影響する?
- 4 4. 実例で見るリフォームの失敗
- 5 5. 工務店に頼んだ方がいいリフォーム
- 6 6. リフォーム屋さんが得意なこと
- 7 7.リフォームで建築確認申請が必要な工事とは?(増築・法22条・防火地域対応)
- 8 8. 【法改正2025年4月】4号特例縮小と確認申請の新ルール
- 9 9. 建設業許可と500万円以上リフォームの違法リスク
- 10 10. 契約分割の抜け道は法律違反!分割契約の注意点
- 11 11. よくあるQ&A
- 12 12. ✅ リフォーム前チェックリスト
- 13 13. まとめ:家を“直す”ではなく、“守る”という考え方
1. リフォーム屋さんとは?
リフォーム屋さんは、もともと職人さんが独立して始めたケースが多い気がします。
例えばですが
クロス(壁紙)職人
設備(トイレ・水道)職人
塗装職人
といった「専門工種」からスタートして、徐々に仕事の幅を広げていったパターンが多いと思います。
そのため、見た目を整える工事や部分的な修繕にはとても強いという特徴があります。

2. 工務店とは?
一方で工務店は、家全体を設計し、構造まで管理できる建築の専門家集団です。
新築住宅を建てられる(建設業許可あり)
耐震・断熱など性能向上リフォームに対応
設計士と連携して工事を進める
つまり、「この壁、抜いても大丈夫?」「この断熱材で足りる?」といった、家の骨組みや性能にかかわる判断ができるのが工務店の強みです。

3. 成り立ちの違いが何に影響する?
たとえば「壁を取り払ってリビングを広げたい」とき、
リフォーム屋さん → 仕上げをどうする?クロス?塗装?

工務店 → 構造
壁か?梁補強が必要か?断熱性能への影響は?
このように、家をどの視点で見ているかが違うんです。

4. 実例で見るリフォームの失敗
① キッチンを移設 → 排水詰まり多発
床下の勾配や配管の設計を考慮せずに工事を進めてしまい、逆流や詰まりが発生。

② 柱を抜いたら…天井がたわむ
構造計算せずに柱を撤去。
数ヶ月後に天井が下がり、再工事に。

③ 内装はおしゃれ → でも冬が寒い
断熱性能を無視してリフォーム。光熱費が上がり、住み心地が悪化。

5. 工務店に頼んだ方がいいリフォーム
間取り変更を含む大規模工事

耐震補強や構造の変更を伴う改修
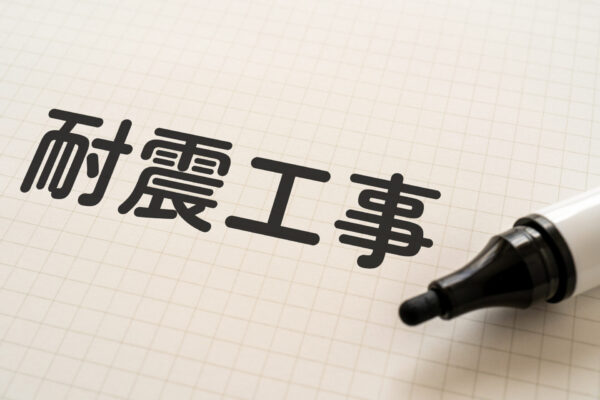
床下・天井裏のやり直し

断熱・気密性能アップ

長期的に安心できる住まいへのリフォーム

6. リフォーム屋さんが得意なこと
壁紙の張り替え

トイレや洗面の入れ替え(配管変更なし)

フローリングの張り替え(構造に問題なければ)

コンセント・スイッチの追加

部分的な修繕や補修
7.リフォームで建築確認申請が必要な工事とは?(増築・法22条・防火地域対応)
増築(10㎡以上)
建築面積・容積率の変更
耐震補強による構造変更
間取り変更や階段位置の変更
🔍補足:10㎡未満でも確認申請が必要な場合
| 地域 | 増築時の確認申請 |
|---|---|
| 防火・準防火地域 | 面積問わず申請必要 |
| 法22条地域のみ | 10㎡未満なら申請不要(原則) |
8. 【法改正2025年4月】4号特例縮小と確認申請の新ルール
これまで木造2階建て以下の建物は「4号特例」で確認申請が一部免除されていました。

しかし、2025年4月から以下のように変更されました:
| 建物の分類 | 対応内容 |
|---|---|
| 木造2階建て・延床200㎡超 | 「新2号建築物」→確認申請が必須 |
| 木造平屋(200㎡以下) | 「新3号建築物」→一部省略可能 |
スケルトンリフォームや2階の増築も、今後は確認申請が必要になるケースがほとんどです。
9. 建設業許可と500万円以上リフォームの違法リスク
リフォームを請け負うには、建設業の許可が必要なケースがあります。
| 工事金額(税込) | 許可の必要性 |
|---|---|
| 500万円以下 | 許可なしでOK(軽微な工事) |
| 500万円超 | 建設業許可が必須 |
許可がないまま請け負えば、違法行為となり、保証や保険も適用されない可能性があります。
過去に建設業の看板について書いたブログ。
建設業許可とは?
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う際に必要な国(または都道府県)の認可です。
許可は大きく「一般建設業」と「特定建設業」に分かれ、さらに工事の種類によって29業種に細分化されています。
たとえば:
建築工事業(建物の新築・増改築など)
大工工事業(木造建築の構造部分)
内装仕上工事業(クロス・床材などの内装)
塗装工事業(外壁や屋根の塗り替え)
電気工事業(照明や配線)
管工事業(水道・給排水・ガス配管)
つまり、業者が「建設業許可を持っている」と言っていても、その工事内容に合った業種の許可を持っているかどうかが非常に重要です。
たとえば「塗装工事業の許可しか持っていない会社」に、構造に関わるようなフルリノベーションを頼むのは、法律的にも技術的にも無理がある場合があります。
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う際に必要な国(または都道府県)の認可です。
工事1件あたりの金額が**税込500万円以上(材料費込み)**の場合、建設業許可が必要
無許可で請け負うと建設業法違反となり、罰則の対象になる可能性もあります
▸ たとえばこんな例:
キッチン+リビングの大規模改修で600万円 → 許可が必要
外壁塗装と屋根改修で合計550万円 → 許可が必要
小さな修繕を複数分割して合算で500万円超 → 実質的に一体と見なされれば許可が必要
▸ 一般建設業と特定建設業の違いも知っておこう
建設業の許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。
一般建設業:税込500万円以上の工事を請け負うために必要な基本的な許可
特定建設業:元請けが下請けに発注する金額が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)になる場合に必要な許可
つまり、元請けとして大規模な案件(マンションのフルリノベーションや商業ビルの改修など)を取りまとめる場合、特定建設業許可がなければ違法となります。
これは一般の人にはなかなか見分けづらい点ですが、「この会社が本当に許可を持っているか」「どこまでの規模の工事が可能なのか」を事前に確認することが大切です。
建設業許可番号やその種別(一般 or 特定)は、会社のホームページや名刺、見積書に明記されていることが多いので、依頼前に必ずチェックしておきましょう。
リフォームでも、増築やフルスケルトンリノベーションなど、予算が大きくなればなるほど、この違いが関わってきます。
10. 契約分割の抜け道は法律違反!分割契約の注意点
悪質な業者の中には、こんなことを言う場合があります。
「じゃあ契約分けますか?
解体工事250万+内装工事250万で…」

でも、これも建設業法で明確にNGです。
▸ 工事が“実質一体”と見なされる場合はアウト
たとえ契約を2本に分けても、
工事内容がつながっていれば500万円を超えたと判断されます。
分割契約でごまかす
材料費だけ後日請求
第三者経由で形式上の分離
↑すべて違法です。
✅ 「分けましょう」と言われたら要注意
それを言う業者は、本来やってはいけないことを当然のようにやろうとしている人たちです。
信頼できる業者なら、最初から「この工事には許可が要るので、ウチではできません」とはっきり言ってくれます。
11. よくあるQ&A
Q:工務店って高くない?
→ 設計・構造・性能まで含んでるから見積もりは高く見えますが
結果的に再工事のリスクが減り、長期的にはコスパ高めです。
Q:500万円以下ならどこに頼んでもいい?
→ 工事内容によります。
構造や断熱が絡むなら、金額にかかわらず工務店レベルの対応が必要なことも。
Q:建設業の許可って、どんなときに必要なの?
A:工事金額が税込500万円以上(材料費含む)のリフォームを請け負う場合、建設業許可が必要です。
これがない業者に依頼すると、違法工事となりトラブルの原因になることもあります。
Q:特定建設業って、どういうときに必要なの?
A:元請けが下請け業者に5,000万円以上(建築一式工事なら8,000万円以上)を発注する場合、特定建設業の許可が必要です。
一般的な戸建てリフォームで必要になることは少ないですが、大規模マンションリノベーションや複合施設の改修工事などでは関係してきます。
Q:許可があるかどうかは、どうやって確認するの?
A:会社のホームページや名刺、見積書などに「建設業許可番号」が記載されていることが多いです。
不明な場合は、国土交通省の建設業者検索システムなどで調べることも可能です。
12. ✅ リフォーム前チェックリスト
| チェック内容 | ✔️ |
|---|---|
| 工事は50万円以上かかる予定 | ✅ |
| 間取り変更を考えている | ✅ |
| 耐震性能も上げたい | ✅ |
| 床下や配管も古くなっている | ✅ |
| 断熱・気密を高めたい | ✅ |
| 性能向上も視野に入れている | ✅ |
| 建築確認申請が必要な可能性がある | ✅ |
| 建設業の許可を確認していない | ✅ |
| 契約を分けようとしていないか不安 | ✅ |
| 一生に一度のリフォームになるかも | ✅ |
あなたはいくつ当てはまりましたか?
6つ以上なら、まずは工務店に一度相談することを強くおすすめします。
小さな費用で済ませたつもりが、大きなやり直しにつながることもあります。
13. まとめ:家を“直す”ではなく、“守る”という考え方
見た目を変えるのは簡単。
でも、家の中身(構造・断熱・法規)を見据えた工事ができる業者かどうかが、
暮らしの快適さ・安全性に直結します。
しかも今は、法改正や許可制度の強化により、
間違った相手に頼むと違法リフォームになってしまう時代です。
「どこに頼むか?」をちゃんと見極めて、
安心・安全なリフォームを進めていきましょう。